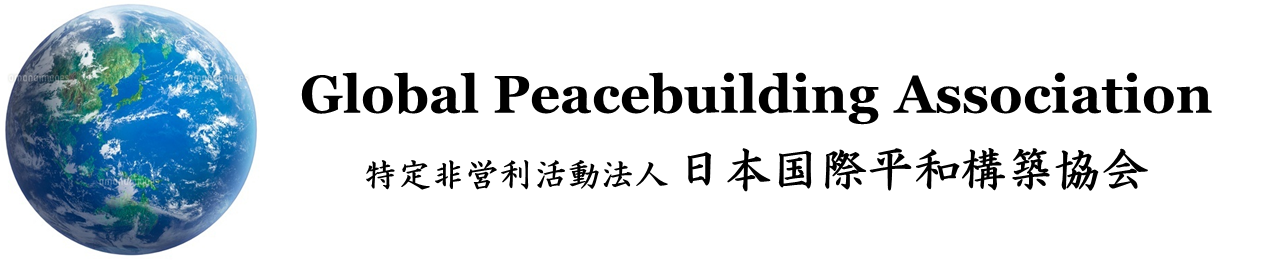京都国際平和構築センターの評議会において、元ユネスコ特命全権大使であり同センター評議員で国際平和構築協会副理事長の山本忠通氏が、文化遺産の保護と国際的な知の交流「越境知」について次の見解を述べた。
山本氏はまず、神余大使の発言に全面的な賛意を示し、文化財保護の重要性を強調した。その関連で、今年2月、笹川平和財団との協力により、アフガニスタン国立博物館館長を含むタリバン代表団を日本に招いた経験を紹介し、その際、東文研や博物館と連携して文化財保護の作業をデモンストレーションし、文化財保護が、国と民族のアイデンティティに取って重要なことについての理解を深めたことを報告した。また、故平山郁夫氏がアフガニスタンの流出文化財が散逸しないように私財で以て市場から買い戻し、これをアフガニスタンに返還寄贈しているが、それらは、山本大使達一行がアフガニスタンを訪問した際、国宝級の彫像である「ゼウスの足」も含みアフガニスタン国立博物館に展示されていた。このことは、バーミヤンの大仏破壊をしたタリバンではあるが、文化遺産が民族の歴史とアイデンティティを象徴することへの理解が深まっていることを示すものであろう旨述べた。タリバン側も今後、日本からの技術・知見の協力を望んでいるという。山本氏は、神余大使が指摘した「状況に応じた適切な協力」の方向性が実現可能であると述べた。
続いて山本氏は、「一万人のキューブアート」企画について言及し、仮に「平和と文化」をテーマとするならユネスコとの連携を検討することも一案であると提案した。ユネスコが推進する「平和の文化」理念を背景に、国際的後援を得ることでイベントの規模と影響力を飛躍的に高められると述べた。「ユネスコは、新しい事務局長を近く選任する段取りであり、そのような中で、この企画を国際的枠組みの中に位置づけることが出来ると望ましいと結んだ。
また、山本氏は「越境智」に関する発言でも、現代の知の在り方に警鐘を鳴らした。アメリカが人の受け入れを選択的に行っていく方向性を打ち出しているる現状や、中国が国家政策と結びつけた知の仕組みを持つことを指摘し、それらは純粋な「越境智」推進の理想から離れていることを指摘した。さらに、ヨーロッパのエラスムス計画は、「越境知」の持つ知的成果よりも、むしろ「他者理解と多様性体験」を狙いとしているところ、今後の留学の在り方を検討するに当たっては、知的側面だけでなく、このような多様性と諸外国に対する理解の深まりの重要性にも着目すべきと考える旨述べた。最後に、産業界が求める「智」の方向性――競争と協力の両立か、協力一辺倒の未来か――について問題提起を行い、「今後の国際社会における知の形成を、現実的かつ倫理的観点から再考すべきである」と訴えた。
他の方の発言や、式典の詳細はこちらからご覧ください。
(レポーター 井門孝紀)
【発言原文(日本語)】
発言1:まず、神余大使のお話に触れたい。私も彼の指摘に100%同意する。 世界の文化財保護については、新聞報道などでも取り上げられている。今年の2月に笹川平和財団と協力してタリバンを日本に招いた。その際、日本でさまざまな議論を行ったが、その中で文化財と文化遺産の保護をも話題とした。単に意見を交わすだけでなく、実際に東文研の協力を得て、文化財保護の実際の作業を説明したり、たり、博物館を訪れ、実地で作業も見せた。タリバンの訪問者も、いかに彼らがアフガニスタンの文化財保護に努力してきたかを理解することが出来たと思う。故平山先生が市場に流出したアフガニスタンの文化財を買い戻し、アフガニスタンに返還する活動をしていたことを、ご遺族の方の証言も交えながら、説明し、その重要性を共有した。 タリバン側の招待者の中には、国立博物館の館長もおり、平山先生が散逸・流出したアフガニスタンの文化財を買い戻し、返還する活動をしていたことを評価していた。我々が、今回の訪問に先立ち、アフガニスタンを訪問した際には、国立博物館を訪問した。バーミヤン大仏を破壊した団体であることから、平山先生の返還した文化財の返還後の扱いに懸念もあったが、実際に博物館をを訪れると、返還された「ゼウスの足」と呼ばれる国宝級の彫刻が博物館の最も重要な場所に展示されていた。これは文化財が国家にとって歴史やアイデンティティを示す重要な存在であり、民族そのものを守ることにつ ながるという認識についての理解が深まったことを示すものと思われる。タリバン側は今後も日本から文化財保護の協力や技術協力、知見提供を望んでいる。したがって、神余大使 がおっしゃった方向性は十分に通じるものであり、状況に応じて適切な協力の可能性は残されてい ると考える。 次に「一万人のキューブアート」の企画について触れたい。テーマはまだ決定していないようだが、も し「平和と文化」を主題とし、芸術や工芸的要素を盛り込むのであれば、ユネスコとの連携を検討することも一案であろう。私がユネスコ代表部にに勤務していたころ、ユネスコはそのような展示を積極的に歓迎していた。もちろん、正式な働きかけや相応の努力が必要となるが、もしユネスコが後援できるような形にできれば、イベントの規模や影響力は格段に広がる。ユネスコは「平和の文化」を推進する国際的な主要機関であり、かつては政治的な要因で注目されにくい時期もあったが、現在は再評価されている。したがって、ぜひユネスコとの関係構築を進め、この企画を国際的な枠組みの中で位置づけることを強く望む。 発言2:例えば、現在のアメリカの動きを見てみると、どのような人を自国に受け入れるかについて、非常に選択的に行っている。これはもはや純粋な「越境智」とは言えないのではないか。では中国はどうか。中国も同様に、国家の政策と越境智との関係を強く意識した仕組みを持っているのではないかと推察する。 第2点目として、ヨーロッパについて触れたい。ヨーロッパでは学生が他国に行き勉強することが義務的に課されている場合がある。だがその目的は、必ずしも「知のための越境智」とは言えないのではないか。理論上、自国内で教育が完結できるのであれば、留学する必要はなく、ネットワークを通じた情報交換だけで済むはずである。しかし、エラスムス計画の本質は、自国で教育できないからではなく、他国に赴き互いを知り、国への理解を深め、多様性を直接体験することにある。この側面が失われてしまうことが問題であると考える。 第3点目は、産業界やビジネス界が「智」に対して何を求めているのかという点である。将来に向けて、国際的な知の体系を築き上げることが必要とされているのか。それとも、競争のない協力一辺倒の世界を目指すべきなのか。あるいは、国際協力と国際競争の双方を並行させていくことが現実的なのか。この点についても議論すべきである。 以上の3点について、お考えを伺いたい。