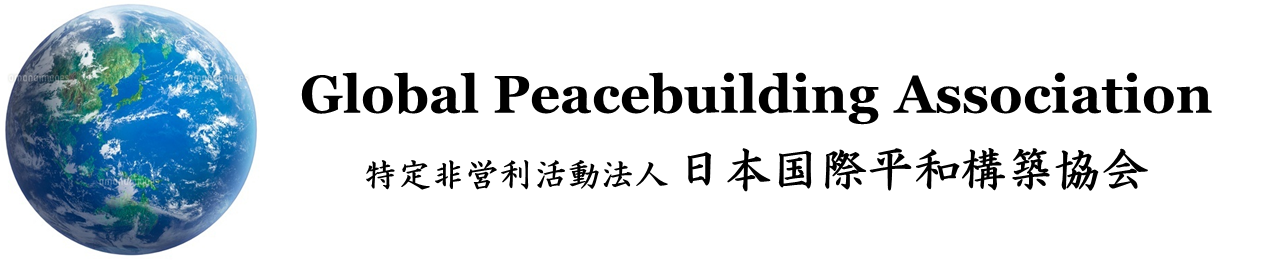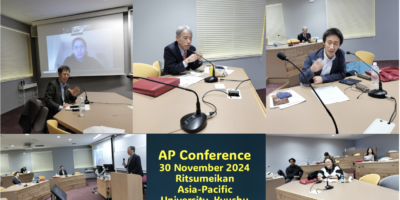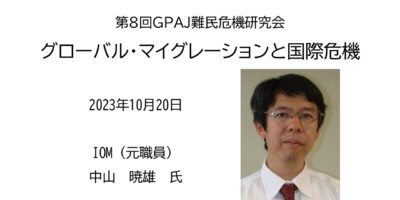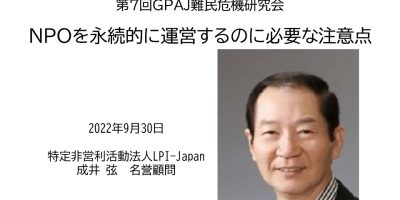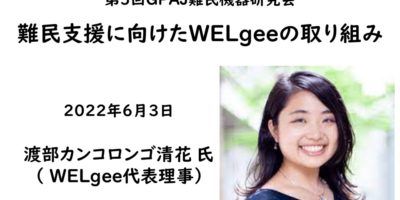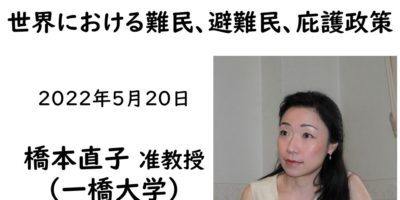難民危機研究会
難民危機研究会発表レポート(20/06/2024)
世界的な人道危機に直面しているミャンマーにおける避難民の現状と課題について、主に ミャンマー北部地域の現地人道支援専門家を交え、現在の政治経済状況や、食料やシェルタ ー支援、教育支援、市民社会への支援についてプレゼンテーションののち、参加者と今後の 支援のニーズや国際社会に求められる支援のあり方等につき議論した。(20/06/2024)
詳細はこちらをクリックしてください。
第8回GPAJ難民危機研究会『グローバル・マイグレーションと国際組織』(20/10/2023)
世界の人の移動の現状について概観。人の移動に影響を与える世界的変化、移民の定義、様々な移住の形態に触れつつ、近年更に急増する不正規移住・混合移住(Mixed Migration Flows)に伴い地中海ルートや中南米・北米ルートで多数の移民が犠牲になっている状況を指摘。第二次世界対戦後の欧州における難民・避難民・余剰人口対策のために設立されたIOM(設立時の名称はICEM)が2016年に国連機関になるまでの歴史をたどりつつ、国連システムによる「安全で秩序ある正規の移住のためのグローバル・コンパクト」(2018年採択)の実施状況、今後の移住政策へのコロナ禍の教訓、人の移動に関連するSDGsの分野における人道・開発・平和の連携(ネクサス)の実践例などを紹介した。喫緊の課題としては、人の移動と関連するグローバル課題(気候変動など)における多国間協力の推進と台頭する自国優先主義や反移民感情の克服。また日本で地方自治体を中心に独自の発展を遂げてきた「多文化共生」の意義にも触れ、グロバールな視点から日本国内・地域社会における移民の社会統合を進めていく事の重要性を強調した。発表後の意見交換では、移住政策におけるIOMの提言活動、IOMとUNHCRの連携、国連システムにおける将来的なIOMのステータス、正規移民・不正規移民への対応、日本の将来的な移民の社会統合における課題などが議論された。
第7回GPAJ難民危機研究会『NPOを永続的に運営するのに必要な注意点』(30/09/2022)
多くの日本への難民をサポートするには「行政に認証された」「NPO法人」の設立が望ましいと思います。しかし、NPO法人の設立・運営に関しては多くの誤解が存在すると感じます。私は2000年にOpen Source Software (OSS)を扱うIT技術者の技術力を認定する特定非営利活動法人を設立し、OSSの分野では世界で最も多くの認定技術者を生み出すことが出来ました。上記の経験から私が学んだことを説明し、難民を助けるNPO法人の設立や既存のNPO法人の運営に役立てて頂ければ幸いですと、成井弦氏が述べられた。詳細はこちらをご参照ください。
第6回GPAJ難民危機研究会『日本の難民入管問題の現情』(15/07/2022)
冒頭、事務局より、日本の難民受入れの現状を説明したうえで、日本の難民認定は政治的に行われているのかとの問題提起がなされたのち、人権弁護士として長年、日本の難民受入れ制度の改善に尽力している大川弁護士から、日本の入管の問題や、難民認定の実情、入管法改正等について、具体的事例を交えながら説明していただいた。
第5回GPAJ難民危機研究会『難民支援に向けたWELgeeの取り組み』(03/06/2022)
第5回研究会では、日本における難民および難民申請者の支援活動の前線に立って活躍されている渡部カンコロンゴ清花氏(WELgee代表理事)を講師としてお招きし、WELgeeの取り組みについて紹介していただいた。
第4回GPAJ難民危機研究会『世界における難民、避難民、庇護政策』(20/05/2022)
昨年8月から実施された主要ドナー国によるアフガニスタン協力者の退避支援が紹介され、アメリカ、ドイツ、英国、カナダ、豪州に比べ、日本の退避支援が、受け入れ数の少なさに加えて、日本に協力したNGO職員の家族滞同を認めない、民間招聘の退避者に対しては日本人の身元保証人や雇用先の確保を求めるなど受け入れ条件が甚だしく厳しい実態が指摘された。
第3回GPAJ難民危機研究会『難民・国内避難民の発生と帰結』(08/04/2022)
第3回GPAJ難民危機研究会では、現在の世界における難民や国内避難民をめぐる諸問題に関する知識・理解を深めるべく、以下のように報告がなされた。第一に、近年の強制移動の動向について、統計データを参照しながら概観した。第二に、学術研究において強制移動がどのように捉えられているのかについて議論した。第三に、強制移動の発生要因は多様であるが、それはpush要因とpull要因に大別できることが示された。第四に、事例紹介として、パキスタン北西部地域で発生した国内避難民とその背景・要因について独自の質問票調査の分析結果を示して議論された。以上のような報告に基づき、研究会参加者によるコメントの提示がなされた。そこでは、難民・国内避難民の定義や発生要因の多様性、ウクライナの現況をめぐる問題、米国、ドイツ、フランスなどにおける難民・移民の受け入れの状況、日本による難民の受け入れや支援の可能性など多岐にわたる論点について活発な議論が取り交わされた。