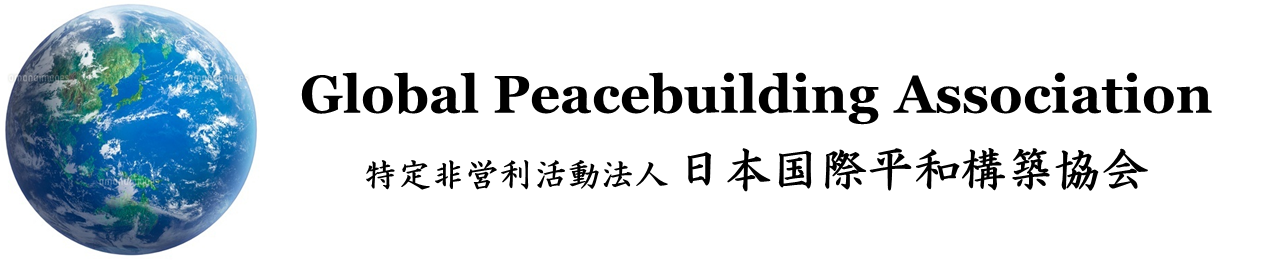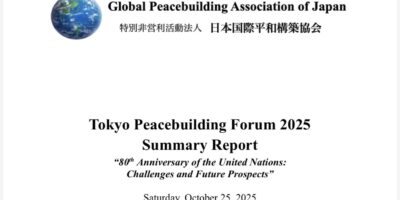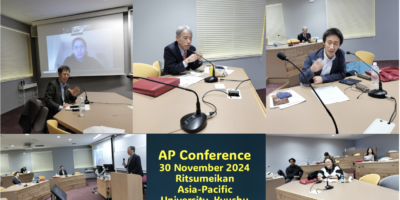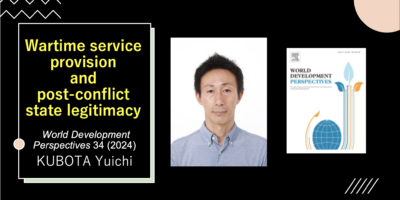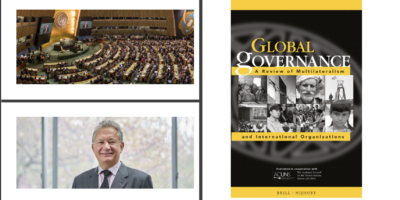5. 会員活動報告
【セミナー報告】2024年9月26日にGPAJオンラインセミナー「スーダン:現状と開発パートナーによる取り組み」を開催しました。(26/09/2024)
スーダンでは2023年4月に軍事衝突が発生して以来、17ヶ月が経ちますが、依然紛争は継続し、人々の生活状況は一層困難になっています。本セミナーでは石原陽一郎氏(世界銀行スーダン所長)と久保英士氏(JICAスーダン事務所長)より、スーダンの現状とそれぞれの機関の活動状況について説明があった後、参加者とともにディスカッションを行いました。(26/09/2024)
窪田氏ほかが紛争時のサービス提供と市民の国家意識について議論(16/09/2024)
紛争後社会の復興に際しては平和な環境が重要であるものの、そうした社会では国家の正当性に関する土台が欠如しているため、暴力の不在自体がすぐさま発展に向けた動きにつながるわけではない。当該論文では、市民が持つ国家の正当性に関する認識が紛争時の公共サービスの経験によってなぜ、またどのように高まる(もしくは低まる)のか、について検討している。
【セミナー報告】2024年8月30日にオンラインセミナー「紛争影響下における気候安全保障」を開催しました。(30/08/2024)
【セミナー報告】2024年8月30日にオンラインセミナー「紛争影響下における気候安全保障」を開催しました。気候変動は我々の日常生活により深刻な影響を及ぼす要因となっていますが、本セミナーでは特に、気候変動が「紛争」や「平和構築」にどのように関わるかを議論しました。気候変動は紛争の過程に影響を及ぼし、また紛争が環境悪化の一因となっています。本セミナーでは、地球環境戦略研究機関(IGES)の岡野直幸研究員と日本国際平和構築協会(GPAJ)の坂根宏治理事より気候安全保障に関する最新の議論の状況を紹介するとともに、紛争のリスク低減のために気候変動にいかに取り組むべきかについて議論しました。(30/08/2024)